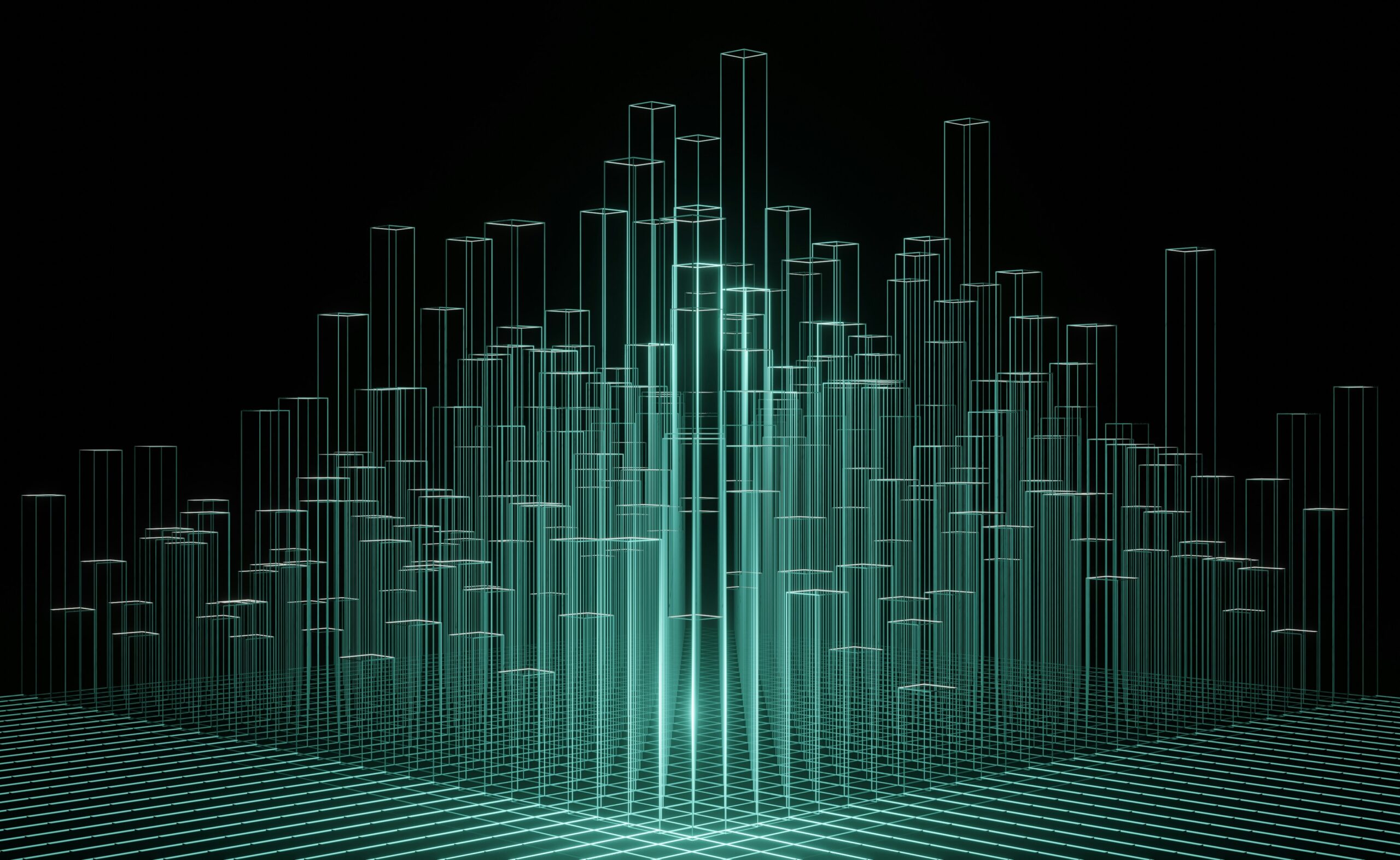「求人を出しても、まともな応募が来ない」
「やっと採用したと思ったら、すぐに辞めてしまう」
「結局、毎年同じような採用活動を繰り返している…」
会社の将来を左右する「採用」という課題について、このような堂々巡りに陥ってはいないでしょうか。もし、少しでも思い当たる節があるのなら、その根本原因は場当たり的な採用活動にある、と断言できます。
採用は、人手が足りないから補充する「作業」ではありません。会社の未来を創るための「投資」です。そして、その投資効果を最大化するための設計図こそが「採用戦略」に他なりません。
この記事は、よくあるキレイゴトの採用論ではありません。これまで数多くの中小企業の現場に伴走してきた我々が、明日から現場で使える、泥臭くも本質的な採用戦略の立て方を、包み隠さずお伝えします。この記事を読み終える頃には、貴社の採用が抱える課題の正体と、それを解決するための具体的な道筋が見えているはずです。
そもそも採用戦略とは何か?
まず、「採用戦略」という言葉の定義を正しく理解し、なぜ今それが必要なのか、腹落ちさせていただきたいと思います。
「採用活動」と「採用戦略」は、全くの別物
採用戦略とは、会社の経営目標を達成するために、「どのような人材を」「いつまでに」「何人」「どうやって仲間に引き入れるか」を描いた、一貫性のある計画のことです。
- 採用活動(戦術):
欠員が出たから求人サイトに載せる、面接をするといった、目先の穴を埋めるための個別の行動。 - 採用戦略(戦略):
3年後の会社の姿から逆算し、勝つべくして勝つための採用の全体方針。
つまり、行き当たりばったりで戦うのではなく、経営という大きな絵図の中で、採用を効果的な一手として機能させることが、採用戦略の核となります。
「人手不足」という“言い訳”の終わり
「今はどこも人手不足だから仕方ない」 この言葉は、思考停止のサインです。確かに、労働人口の減少や働き方の多様化により、人材獲得の難易度は上がっています。
しかし、厳しい環境下でも、着実に自社に必要な人材を採用し、成長を続けている企業が存在するのもまた事実です。その差は一体どこにあるのでしょうか。
答えは単純明快です。彼らは採用戦略を持っています。
- 労働市場という戦場で、自分たちの武器(魅力)が何かを理解している。
- 戦うべき相手(採用ターゲット)を明確に定めている。
- そして、最も効果的な戦い方(採用手法・選考)を計画的に実行している。
情報が溢れ、候補者の目が肥えた現代において、無戦略な採用はもはや通用しません。「人手不足」を嘆く前に、まずは自社の採用が「戦略」と呼べるレベルにあるか、胸に手を当てて考えてみてください。
【警告】採用戦略で、中小企業が陥る「3つの罠」
具体的な立て方の解説に入る前に、我々が現場で見てきた、多くの中小企業が陥りがちな典型的な失敗パターンを3つ共有します。反面教師として、自社に当てはまっていないか確認してください。
罠1:社長の「とにかく、いい人採ってくれ」病
これは最も多い失敗です。経営目標と採用が全く連動しておらず、「どんな人が欲しいのか」が曖昧なまま、「とにかく優秀で、やる気のある、いい人が欲しい」と担当者に丸投げしてしまう。これでは、担当者は誰に何をアピールすればいいか分からず、結果的に誰の心にも響かない、当たり障りのない求人しか作れません。
罠2:自社の「武器」を勘違いしている
「ウチは給料や待遇では大手に勝てないから…」と、戦う前から諦めてしまうケースです。しかし、候補者は給料だけで会社を選んでいるわけではありません。事業の社会性、挑戦できる環境、独自の社風など、中小企業だからこそ提供できる価値(武器)は必ずあります。それに気づかず、あるいは言語化できず、魅力を伝えきれていない企業が非常に多いのが実情です。
罠3:面接が「見極める」だけの場になっている
面接を、「候補者の能力を見極めて、選別する場」だと考えているなら、その認識は改める必要があります。優秀な候補者ほど、複数の企業から内定を得ています。彼らにとって、面接は「企業が自分を見極める場」であると同時に、「自分が企業を見極める場」でもあります。候補者の志望度を高めるような「口説き」の視点がなければ、最後の最後で競合に負けてしまいます。
現場で使える、採用戦略の立て方【5つの手順】
では、ここから本題です。机上の空論ではない、実践的な採用戦略の立て方を5つの手順に沿って解説します。
手順1: 会社の「数字」と「言葉」を直視する
採用戦略の出発点は、社内にあります。まずは自社の経営計画書を引っ張り出してください。
- 数字: 「3年後に売上を〇〇円にする」「新規事業で〇〇円の利益を出す」
- 言葉: 「業界No.1の顧客満足度を目指す」「〇〇という領域で社会課題を解決する」
これらの目標を達成するために、**「どんな機能を持つ人材が、いつまでに、何人必要なのか?」を徹底的に考え、書き出します。ここが曖昧なまま進むと、全ての計画が砂上の楼閣になります。
手順2: 「誰が欲しいか」を具体的に描き切る(ペルソナ設定)
手順1で必要な人材の機能が見えたら、次はそれを具体的な人物像に落とし込みます。これを一般的に「ペルソナ設定」と呼びます。
単に「営業経験3年」といったスペックだけではペルソナ設定としては不十分です。
- スキル・経験: どんな修羅場をくぐり抜けてきた経験が必要か?
- 価値観・人間性: どんな企業文化なら水を得た魚のように活躍できるか? 誠実さか、貪欲さか?
- 働く動機: 何のために働き、何を成し遂げたいと考えている人物か?
まるで実在する一人の人間に手紙を書くかのように、解像度高く人物像を描き切ること。これが、後のメッセージ作りや媒体選定の精度を大きく左右します。
手順3: 自社の「武器」を洗い出す(EVPの整理)
次に、手順2で描いたペルソナが、「なぜ競合ではなく、ウチを選ぶのか?」という問いに答えるための「武器」を整理します。
これはEVP(Employee Value Proposition)と呼ばれる考え方で、難しく聞こえますが、要は「ウチで働くと、こんな良いことがある」という従業員への約束を明確にすることです。
- 事業の魅力: この仕事でしか味わえない興奮や、社会貢献性。
- 組織の魅力: 尊敬できる仲間、風通しの良い文化、意思決定の速さ。
- 成長の機会: 若いうちから得られる裁量権、経営陣との距離の近さ。
- 待遇・制度: 給与や福利厚生だけでなく、独自の休暇制度や働き方の柔軟性。
これらの武器を言語化し、候補者の心に突き刺さるメッセージとして磨き上げてください。
手順4: 「どこで、どう戦うか」を決める(採用手法と選考)
武器が定まったら、いよいよ戦場と戦術を決めます。
採用手法(どこで戦うか?)
設定したペルソナが、普段どこで情報を集めているかを考え、最適な手法を選びます。
- 求人広告: 幅広い層に知ってもらいたい場合
- ダイレクトリクルーティング: 指名買いしたい専門人材がいる場合
- 人材紹介: 効率的に候補者と会いたい場合
- リファラル採用: 社風に合う人材を確実に取りたい場合
全てのチャネルに手を出すのではなく、自社のペルソナと武器に最も適した戦場に資源を集中させることが、中小企業の鉄則です。
選考プロセス(どうやって勝つか?)
各選考段階で、「何を確認し(見極め)」「何を伝えるか(口説き)」を明確に設計します。面接官によって言うことが違う、といった事態は絶対に避けなければなりません。一貫したメッセージで、候補者の志望度を着実に高めていくシナリオを描きましょう。
手順5: 「やりっぱなし」にしない仕組みを作る(効果測定)
戦略は実行して終わりではありません。結果を数字で振り返り、改善し続ける仕組みがあって初めて、戦略は機能します。
最低でも、以下の指標は毎月追いかけてください。
- 応募数 / 採用単価
- 書類選考通過率
- 内定率 / 内定承諾率
これらの数字を分析すれば、「どの採用手法の費用対効果が高いか」「選考プロセスのどこにボトルネックがあるか」といった課題が浮き彫りになります。感覚論ではなく、データに基づいて次の打ち手を考える。このサイクルを回し続けることが、採用力を継続的に高める唯一の方法です。
採用戦略を絵に描いた餅にしないための「3つの心得」
最後に、ここまで作り上げた採用戦略を確実に実行し、成果に繋げるための心構えを3つお伝えします。
心得1: 採用は「人事だけの仕事」という思い込みを捨てる
採用の成否は、人事部の頑張りだけでは決まりません。経営者自らがビジョンを語り、現場のエース社員が仕事の面白さを伝える。会社全体を巻き込み、総力戦で臨むという覚悟がなければ、今の時代の採用戦は勝ち抜けません。
心得2: 候補者は「お客様」であると心得る
候補者は、選考される側であると同時に、自社を選ぶ側のお客様です。連絡のスピード、面接官の態度、オフィスの雰囲気。その一つひとつが「候補者体験」となり、企業の評価に直結します。「選んでやっている」という傲慢な態度は、即座に見透かされます。
心得3: 戦略は「生き物」だと理解する
一度立てた戦略が、永遠に通用することはありません。市場環境も、競合の動きも、自社の状況も刻々と変化します。計画に固執するのではなく、最低でも半年に一度は戦略全体を見直し、柔軟に軌道修正を行う。そのしなやかさこそが、戦略を陳腐化させないための鍵です。
まとめ:今すぐ、ペンを取り、書き出すことから始めよう
今回は、中小企業が採用で勝つための、実践的な採用戦略の立て方について解説しました。
重要な点を、もう一度確認します。
- 採用戦略とは、経営目標から逆算した、勝つべくして勝つための設計図である。
- 「目的の曖昧さ」「自社の武器の誤認」「面接の勘違い」がよくある失敗の罠。
- 「①数字と言葉」「②人物像」「③武器」「④戦場と戦術」「⑤仕組み」の5つの手順で、泥臭く戦略を練り上げる。
この記事を読んで「勉強になった」で終わらせないでください。 今すぐペンを取り、まずは自社の経営目標と、それを達成するために本当に必要な人材は誰なのかを、たった一人でもいいので書き出してみてください。
その泥臭い一歩こそが、貴社の未来を切り拓く、最強の採用戦略の始まりなのです。