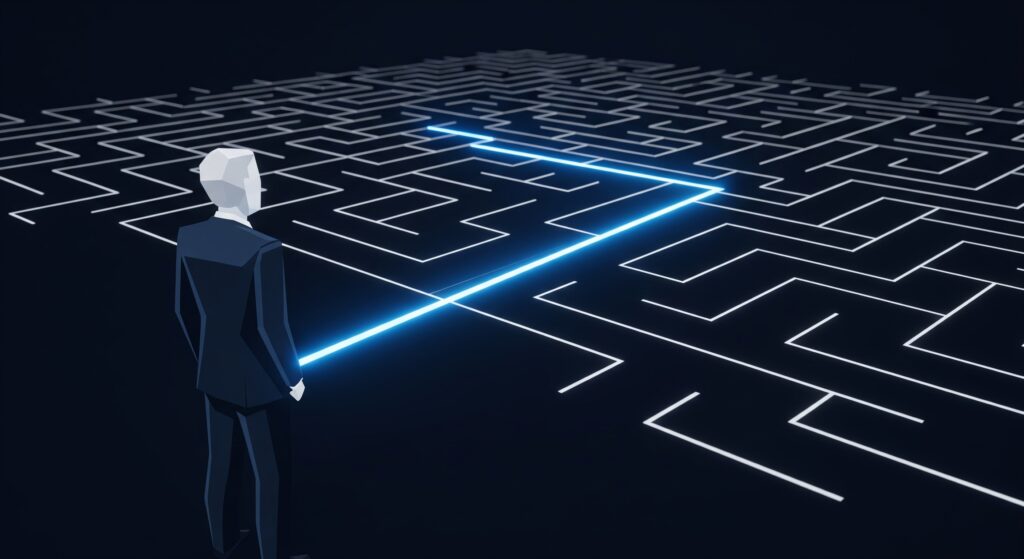現場で発生する問題に、日々懸命に対処している。それなのに、なぜか事態は好転しない。まるでモグラ叩きのように、一つの問題を叩くと、別の場所から新たな問題が顔を出す…。
リーダーであるあなたは、そんな終わりなきループに、消耗しきっているのではないでしょうか。
- 良かれと思って導入した新しい業務ルールが、かえって現場の混乱を招いてしまった。
- ある部門の課題を解決したら、別の部門から「しわ寄せが来た」と不満が噴出した。
- 目先の売上を追うあまり、長期的な顧客満足度が下がってしまった。
もし一つでも心当たりがあるなら、それはあなたの能力や努力が不足しているからではありません。原因は、問題解決に使う「思考のOS(考え方の基本ソフト)」が、現代のビジネスの複雑さに合わなくなっていることにあるのかもしれません。
複雑に要素が絡み合った問題は、一本の縄を力任せに引っ張っても、かえって固く締まってしまう「知恵の輪」のようなものです。
本記事では、この知恵の輪をしなやかに解きほぐすための新しい思考のOS、「システム思考」について、現場の痛みがわかるコンサルタントの視点から、泥臭く、具体的にお話しします。机上の空論はもう終わりです。
その打ち手、逆効果かも?良かれと思った改善が失敗する2つの「ワナ」
私たちは問題に直面すると、過去の成功体験から、つい慣れた方法に頼りがちです。しかし、その「いつものやり方」が、実は問題をより複雑にしているとしたら…?ここでは、多くの企業が陥りがちな2つのアプローチとその限界について、少し耳の痛いお話をします。
ワナ1:一点突破アプローチ(個別最適のワナ)
ある特定の問題に対し、強力な解決策を一つ投入して、一気に突破しようとする考え方です。例えば、「売上が落ちている」という問題に対し、「とにかく営業件数を増やせ!」と号令をかけたり、「最新のITツールを導入して効率化だ!」と一気に推し進めたりするケースがこれにあたります。
確かに、短期的に成果が出ることもあります。しかし、この方法は「木を見て森を見ず」に陥りやすい危険な打ち手です。営業件数を無理に増やした結果、一つひとつの提案の質が下がり、顧客との関係が悪化する。現場が使いこなせない高度なツールを導入したために、かえって業務が滞る。
このように、一つの正解に固執するあまり、他の部分にしわ寄せが及び、結果として全体の状況を悪化させてしまうのです。
ワナ2:顧客第一アプローチ(視野狭窄のワナ)
「お客様の言うことは絶対だ」と、顧客の要望に徹底的に応えようとするアプローチです。高い顧客満足度を得る上で、もちろん大切な考え方です。
しかし、これもまた行き過ぎると危険です。特定の大口顧客の要望を優先するあまり、他の多くの顧客が離れてしまったり、無理な要求に応え続けた結果、従業員が疲弊し、サービスの質が全体的に低下してしまったりする。
顧客という「特定の関係者」に集中するあまり、従業員、協力会社、ひいては自社の経営そのものといった、他の大切な要素への影響が見えなくなってしまうのです。これでは、事業を長く続けることはできません。
解くべきは「個別の課題」ではなく「全体の構造」である
一点突破も、顧客第一も、それ自体が間違っているのではありません。問題なのは、どちらも「部分最適」のアプローチであるという点です。
現代のビジネスは、顧客、従業員、協力会社、市場、社会といった無数の要素が、互いに影響を与え合う複雑な「システム(生態系)」の中で動いています。
だからこそ、思考の転換が必要です。 目の前の「課題」という点だけを見るのではなく、「課題を生み出しているシステム全体の構造、つまり関係性」に目を向ける。
この「全体最適」を実現するための思考のOSこそが、「システム思考」なのです。
システム思考を実践する4つの手順
では、具体的にどうすればシステム思考を実践できるのでしょうか。ここでは、明日からあなたの会社で使えるよう、4つの手順に沿って解説します。
手順1:旗印を立てる(自社の役割を再定義する)
多くの会社は「What(何を作るか、何を売るか)」から事業を考えます。しかし、システム思考の出発点は「Why/How(なぜこの事業をやるのか、社会というシステムにどう貢献するのか)」です。
例えば、ある町の印刷会社が、長年「高品質な印刷物を作ること」を自社の使命だと考えていました。しかし、ペーパーレス化の波で受注は減少の一途。そこで彼らは自社の旗印を「地域の事業者様の“伝えたい想い”を形にする会社」と立て直しました。
すると、どうでしょう。事業は「紙に印刷する」ことだけにとどまらず、Webサイトの制作、イベントの企画運営、動画制作といった、地域の事業者の想いを伝えるための新しいサービスが次々と生まれ、会社の業績はV字回復を遂げたのです。
あなたの会社は、社会というシステムの中で、本当は何をすべきでしょうか?まず、その旗印を明確に立てることから始めます。
手順2:問題の見方を変える(視点を増やし、定義し直す)
一つの問題も、見る人の立場によってその姿は全く異なります。システム思考では、一つの「正しい問題定義」に固執しません。
例えば、「若手社員の離職率が高い」という問題があったとします。 経営者は「最近の若者は根性がない」と見てしまうかもしれません。 しかし、現場の若手社員の視点では「この会社で成長できる未来が見えない」かもしれませんし、人事部長の視点では「評価制度が時代に合っていない」という問題に見えるかもしれません。
このように、関わる人々の視点から問題を多角的に捉え直すことで、「若手の根性を鍛え直す」という的外れな対策ではなく、「キャリアパスを明確にし、研修制度を充実させる」といった、より本質的な打ち手が見えてくるのです。
手順3:流れをせき止める「淀み」を見つける
会社の内部では、常に「モノ、情報、お金」が流れています。イノベーションとは、必ずしも何か新しいものを生み出すことだけではありません。この流れを阻害している非効率な部分、つまり「淀み」を見つけ出し、解消することもまた、優れた改善活動です。
ある製造業では、営業部が受注した仕様が、開発部に正確に伝わらないことが原因で、手戻りが頻発していました。まさに「情報」の流れが淀んでいたのです。 そこで、両部門が共通で使う簡単な情報共有シートを一枚導入しました。たったそれだけで、伝達ミスが激減し、開発スピードが大幅に向上しました。
あなたの会社の業務プロセスには、どこかに流れを悪くしている「淀み」はありませんか?無駄な会議、複雑な承認プロセス、部門間の壁。それこそが、解消すべき根本問題です。
手順4:小さく始めて、全体を動かす「一石」を投じる
複雑なシステムを、一度に完璧に変えようとしてはいけません。それは巨大な船の舵を急に切るようなもので、大きな抵抗と混乱を生むだけです。
システム思考では、一発逆転の特効薬を狙うのではなく、システム全体に良い影響を与える小さな変化、「小さな一石」を戦略的に投じることを考えます。
例えば、全社的に新しい会計ソフトを導入したいと考えたとしましょう。いきなり全社導入を宣言して反発を食らうのではなく、まずはITに詳しい一部署で試験的に導入してもらうのです。 そこで「業務時間が半分になった」「ミスがなくなった」という具体的な成功事例が生まれれば、「うちの部署でも使ってみたい」という声が自然と広まっていきます。
この小さな成功の連鎖が、やがて会社全体の常識を変える、大きなうねりへと繋がっていくのです。
明日からできる第一歩:「関係者マップ」を描いてみよう
理論は分かったが、どこから手をつければいいか分からない。そう感じるかもしれません。そこで、明日からすぐに試せる具体的なワークを一つ提案します。それは、あなたの事業の「関係者マップ」を作成することです。
- 大きな紙の中央に、あなたの会社(もしくは、あなたの担当事業)を置きます。
- その周りに、事業に関わる全ての人々や組織を書き出しましょう。 顧客、従業員、協力会社、株主、銀行、競合、地域住民など、思いつく限り洗い出してください。
- それぞれの関係者が、あなたの事業に対して何を気にしているか(真の関心事)を想像して書き込みます。 例えば、従業員は「給与や働きがい」、銀行は「きちんと返済してくれるか」、地域住民は「騒音や安全性」かもしれません。
このマップを描いてみると、いかに自分が無意識に、自社や特定顧客の視点だけで物事を考えていたかに気づくはずです。この全体像の把握こそが、システム思考の最も重要な第一歩なのです。
まとめ:複雑な時代を乗りこなすための、新しい「思考のOS」
「頑張っているのに、問題が増える」 この現象は、あなたが対峙している問題が、単純な原因と結果で結ばれていない、複雑な「システム」だからです。
この複雑な知恵の輪を解きほぐすには、
- 社会における自社の旗印を立て、
- 多様な視点で問題を見直し、
- 組織内の流れの「淀み」を見つけ、
- 賢い「一石」で全体を動かす
という「システム思考」が、強力な武器となります。
これは単なる問題解決の小手先のテクニックではありません。先行き不透明な時代において、変化にしなやかに対応し、持続可能な事業を創造するための、経営者・リーダーのための新しい「思考のOS」なのです。
まずは、あなたの机の上で「関係者マップ」を描くことから始めてみませんか。そこから、きっと新しい景色が見えてくるはずです。